遠出キャンプより公園で四季を感じるほうが子どもにいい理由
近年、広がりつつある「森のようちえん」。耳にしたことのある読者も多いのではないでしょうか? 自然の中で子どもたちを自由に遊ばせながら育てる幼児教育や保育活動の総称が「森のようちえん」です。忙しないカリキュラムを設けず、子どもの主体性を重視することで、非認知能力がぐんぐん育つと言われています。
ただ、豊かな自然環境が必要なため郊外や地方にあることが多く、都会に住むママにとってはなかなか馴染みがないのも事実。でも、都会でも森のようちえん的体験は十分できるんです。
都会でもできる自然との向き合い方や森のようちえん的育児について、『ルポ 森のようちえん』(集英社新書)を出版した教育ジャーナリスト・おおたとしまささんと、文京区で身近な自然との関わりを重視した保育を実践している、文京区立お茶の水女子大学こども園の元園長・宮里暁美先生の対談をお届けします。
遠くのキャンプ場に行くよりも
近くの公園で四季を感じるほうがいい
——森のようちえんは環境的にも精神的にも、もっとハードルが高いと思っていたのですが、都会に住んでいてもちょっと視点を変えるだけで実現できると知って、すごく新鮮でした。
おおたとしまささん(以下、敬称略): みんな素敵だなとは思うんでしょうけど、「じゃあ、都会で子育てしている私たちは絶望なの?」と思ってしまう。でも、実はそんなことはないということを『ルポ 森のようちえん』では書いていますし、なにより宮里先生は何年も前から東京のど真ん中で実践されていたんですよね。
宮里暁美先生(以下、敬称略): 目黒区の幼稚園にいた20年前ころからですね。その幼稚園は園庭が狭かったので、すぐ近所にあった自然豊かな都立林試の森公園を園庭代わりに使わせてもらっていたんです。それには公園側がすごく理解があったのが有難かったのですが、毎日のようにそこで過ごす中で印象的だったのは、森の生活と園の生活が繋がっていくこと。木漏れ日の中、木と木の間を縫って歩くだけで楽しい。園内で楽しんでいた電車ごっこも森の中でするとイメージがどんどん広がっていく。自然の中に入り込むのはいろんなことを感じる時間だなあと。ただ通り過ぎる公園との接し方を見直して、そこに居続けて入り込み、居場所にしていくといろんなことが変わるということを体験したんですよね。その後、お茶の水女子大学附属幼稚園を経て、運命的に出会ってしまったのが、今も関わっている文京区立お茶の水女子大こども園です。ここも非常に園庭が狭いので、お茶大のキャンパスの敷地を使わせてもらっています。散歩の時にどこを通るか、木の棒を拾うかどうか、水溜まりも発見に満ちていますし、放置された草むらに入り込むだけでもうジャングルなんですよ。一方で、子どもは自然と人工物を分けないので、道端の排水溝が気になったりもする。文京区の真ん中ですけど、そこに魅力を感じようとして何か働きかけると、何かが起こるということを日々実感していますね。
おおた: 緑深い森の中こそが自然だというのは大人の思い込みで、その辺の草むらにいるハサミムシは子どもにとって怪獣なんですよね。
宮里: 本当にその通りですね。共感します。ダンゴムシも身近にいるんですよね。小さい頃、ダンゴムシやハサミムシで遊んでいるはずなんですが、みんな忘れちゃってるんです。自然に出会うなら遠くのキャンプ場に行かなきゃと考えがちで、それはそれでいい経験なんですけど、身近なところに自然はあるよって。
おおた: 遠くの森にビジターとして行くよりも、身近な公園を年中訪れて四季の移り変わりを感じるほうが、子どもの心に残るはずだということなんですね。

天気によって行動を変えない
主導権は人間じゃなくて自然側にある
——自然との触れ合いはどの園でも取り入れていると思うのですが、森のようちえん的な自然との向き合い方についてもう少し教えていただけますか?
宮里: 自然との向き合い方について教えてもらったのは、プロのナチュラリスト佐々木洋さんからでした。佐々木さんに教えていただきながら考案した自然と楽しむ4つのキーワードがあるのですが、まずは拠点を定めて繰り返し行くということ。私も初めは、A地点に行ったら次はB地点に行くのがいい、行く場所を変えることが子どもにとって豊かな経験になると思っていたんですね。でも、同じ場所に何度もずっと通わないと自然が変化していくのも感じ取れないし、そこを拠点としながら地図が広がっていくんだと。佐々木さんから思いこみを指摘されて、保育者としてハッとしました。
もう一つは、旬を逃さないこと。一応、教育機関ですから、年間予定に行事をバランスよく入れるわけですけど、そうすると予定表ありきになりがちで。どんぐり拾いなんかはある程度時期を定めて行きますが、それ以上に佐々木さんに教えられてハッとしたのが、台風の後やすごい風が吹いた後は行ったほうがいいよ、宝物がゴロゴロ落ちてるからって。そう考えると、今は何の花が満開だとか自然側の動きを捉えて計画していく。今咲いているなら、今見に行かなきゃって。主導権は人間の都合じゃなくて、自然側にあるんですよね。
おおた: 森のようちえんは、意図を設定しないでその場に誘われる、そこに身を委ねるという雰囲気が共通していますよね。
宮里: 3つ目は、園と森の生活を繋げること。電車ごっこも面白いですけど、人形劇セットを持って行ったのは特に面白かったですね。“大きなかぶ”をやっても、バックは自然ですから背景を描く必要がないし、通りかかった近所の方が見て笑ってくれるんですよ。4つ目は保護者とともに、森の活動を豊かに展開する。旬を逃さないみたいなことも、何か見頃があったら教えてくださいと保護者通信に書いてみると、情報をもらえたりしますから。
主導権は自然にあるということで言うと、晴れでも雨でも出かけていくのも大事ですね。大人はつい、都合のいい時に行きたがりますよね。天候が良くて穏やかな時を選んだり、逆に今日は雨だから行けないとか。そうじゃなくて、安全は担保した上でどんな時でも行くんです。我が家はキャンプが好きで天気を問わず行っていたのですが、はじめは雨のキャンプは大変だと思ったけど、だんだんと雨の日だって素晴らしいなぁと気づいて。いろんな天候だからこそ味わえることがありますよね。
おおた: 晴れは良い天気で、雨が悪い天気なんていうのも本当はなくて、そういう価値観自体が薄らいでいってありのままを受け入れて、逆に受け入れてもらっていることも気づいて。そういう価値観で子どもに接するといろんなことに気づきますよね。
宮里: だって、全部必要なんですもんね、この地球が保たれる上で。こちらの都合だけで動くと豊かな経験をするチャンスを逃しちゃうんだなぁって。でもそれには、それがいいって思わないと。なかなか雨の日にカッパを着て出かけないですけど、子どもは雨の日、大好きですから。
あと、私が今いる園は保育時間を長めに取っているので、遠足にゆっくり行くことができるんです。先日も5歳の子たちと小石川植物園に行ってきたのですが、他の団体が帰った後にちょっと長くいるのがとても好きで。水族館やどこに行っても、とりあえず長くいることにしてるんです。そうすると何通りもの楽しみ方があったり、子どもが自分で何か始めたりするのが面白い。プログラムで区切らずに、その場の空気やその子なりの何かを感じるまでのんびりするのは、森のようちえん的かなぁと思いますね。
Profile

宮里暁美さん
国立大学法人お茶の水女子大学 アカデミック・プロダクション特任教授。元文京区立お茶の水女子大学こども園園長。「耳をすますこと、目をこらすこと」を心がけ、30年以上保育の現場や保育者育成に従事する。著書に『子どもたちの四季』(主婦の友社)など。3児の母。
Profile

おおたとしまささん
教育ジャーナリスト。1973年東京都生まれ。東京外国語大学中退、上智大学英語学科卒。リクルートから独立後、育児・教育分野で活躍。執筆・講演活動を行う。
著書は『中学受験生に伝えたい 勉強よりも大切な100の言葉』(小学館)など60冊以上。
http://toshimasaota.jp/
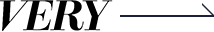


































































































![.
本日から、滝沢眞規子さんに着こなしてほしい、
メゾンの最旬夏ファッションをお届けします♡
初日の本日は、【LOEWE】。@loewe
毎シーズン、捻りのある個性派デニムで
着こなしに真新しさをくれるロエベ。
今季は、メゾンのアイコンでもある
〝フラメンコ〟から着想を得たジーンズが登場。
フラメンコバッグのように立体的なウエストは、
「腰位置を落としてはく方がバランスよく見える」
と滝沢さん。
くびれの美しさが際立ちます🙌
スリムフィットのタンクトップに
デニムはあえて、ローウエストでゆるっと。
大胆なメリハリバランスもデニムを
モードに昇華する秘訣です。
――
タンクトップ¥128,700デニムパンツ¥168,300シューズ¥171,600バッグ¥649,000ピアス¥126,500右手バングル¥113,300左手バングル[細]¥148,500[太]¥171,600(ロエベ/ロエベ ジャパン クライアントサービス 03-6215-6116)
—
Model/MAKIKO TAKIZAWA @makikotakizawa
Photographer/TAKESHI TAKAGI<SIGNO> @takagi_takeshi
Styling/MIE SAITO
Hair/KENJI IDE<UM> @kenji_ide
Make-up/MARIKO SHIMADA<UM> @mariko_shimada
Writing/YUKA SAKAMOTO @yukasakamoto924
Composition/AYAKO ISONO
#loewe#ロエベ
#フラメンコ#フラメンコジーンズ
#滝沢眞規子#タキマキ
#タキマキsummer2025
#VERYNAVY#VERYNAVYWEB](https://veryweb.jp/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
