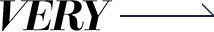【中学受験】を笑顔で乗り越えるための秘訣って?<教育ジャーナリスト・おおたとしまささん>
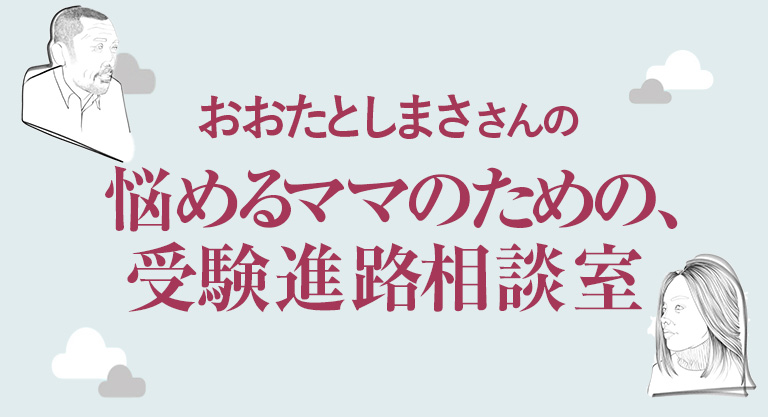
『中学受験生を見守る最強メンタル!』というタイトルで書籍化された、話題の連載・おおたとしまささんの『悩めるママのための、受験進路相談室』。約5年間、中学受験に悩むママの相談を取り上げてきたこの連載もついに最終回。今なお過熱している中学受験ですが、ともに受験勉強に取り組むことで、親子の関係を見直し、成長に繫げるチャンスでもあります。おおたさんの愛あるアドバイスで受験を乗り越えた親子を改めて取材しました。
こちらの記事も読まれています
「弟は全然勉強しないよね」と不満げだった姉が
最後には大きな味方に。
家族全員、笑顔で受験を終えられました
編集部:Kさんには2023年に受験を終えた長女と、2025年に受験した長男の2人のお子さんがいます。長女が受験生の弟に対して、「私のときと比べてママの対応が全然違う」「弟は全然勉強していないよね」と言い出したので、どんな声がけをしたらいいのか悩んでいるというご相談でご登場いただきました。相談を経て、ご家族がどのように変化をしたのか教えてください。
Kさん(相談者):おおたさんに「娘との時間も大切に」とアドバイスをもらったので、2人で過ごす時間をつくりました。その中で、弟と姉の学力や個性の違いについても話しました。娘は暗記が得意だったけれど、息子は苦手。その代わり思考力が高いとか。弟の勉強時間が短いことや私が放任していることに対しても、「弟はこういう個性があるから、ママはこんなふうに対応しているんだ」と理解してくれるようになり、「受験は暗記が多いから大変だよね」と言ってくれるまでになりました。最終的には、模試の結果も家族全員で共有しました。
オ(おおたさん):弟の個性を理解して、自分の基準を当てはめてはいけないと気づいたことで、娘さんも弟のことを親と同じような視点から見てくれるようになったのですね。中学受験を経験した元中学受験生が、どんな精神的な成長を遂げるのかという、とても興味深いお話です。
編:息子さんは今年受験を終えました。相談時点で「本人の意思を尊重する」とおおらかに見守る宣言をされていましたが、受験直前の息子さんの様子やKさんの心境について教えてください。
K:結局最後まで見守り続けました。「宿題やった?」程度の声がけはしましたが、「勉強しなさい」とか「これをやらなきゃダメ」とは言わないように気をつけました。もちろん、不安になることもありましたが、やりなさいと言われてもやらないし、私が怒ってしまうとどんどん勉強を嫌いになってしまう。だから待つことにしました。そうしたら、受験数カ月前になって、いよいよ本人が焦り出したのです。アレクサに「受験まであと何日?」と聞いたり、自分から机に向かうようになったりと、変化が見え始めました。1月中旬に「塾以外に質問ができるところはある?」と聞かれたので、家庭教師を提案したら、「やってみたい」と。急いでインターネットで検索して、大学生のお兄さんに来てもらって、受験直前まで算数や過去問対策を任せました。家庭教師との勉強は自分から言い始めたことだったので、スムーズに、前向きに取り組んでいました。あれほどゲームが好きだったのに、自分から「預かって」と私に託してきたり、「朝走ると強靭な体になれるって塾の先生が言っていた」と、友だちとランニングを始めたり。今までの息子からは考えられない行動が見られました。
オ:息子さん自身から「変わりたい」という欲求が出てきたのですね。今できることを、自分なりに頭を使って考えていたということが伝わってきます。ありきたりな表現ですが、中学受験の機会を通して大きな内面の成長を成し遂げたのだと思います。目先の点数を上げることよりも、そういった経験をしていくことのほうが長い人生においてはよほど価値が大きい。それができたのも、「お母さんは自分を本当に信じてくれている」という信頼が息子さんに伝わったからだと思います。何かしてくれたから信じるのではなく、親が先に子を信じたからこそ、それに応えたいと考えたんじゃないでしょうか。
編:息子さんが徐々に変化していく中で、どのような受験本番を迎えられたのでしょうか。
K:当初、息子は第一志望に落ちたら公立に行くと決めていました。でも私たち親も塾の先生も、ここまで頑張ってきたということもあって、どこかの私立には進学させてあげたいと思い、息子に内緒で何校かに願書を出しておきました。準備期間が少なかったこともあって、第一志望の学校は4回受けて、4回とも不合格でした。その結果を受けて、「他の学校も受験したい」と息子が自分から言い出しました。それでこっそり願書を出していた2校も受験しましたが、どちらも不合格で…。さすがに焦りましたが、息子はへこたれず、「7日まで続いたとしても、俺は受け続ける」って。塾の先生に相談して、おすすめしてもらった学校を急きょ受験しました。そこで4日目にしてようやく合格をいただきました。ノーマークの学校でしたが、受験の待ち時間に聞いた説明会の内容がよく、親の私たちも気に入りました。息子本人もようやく合格をもらえたのがすごく嬉しくて、半端ない喜びようでした。本人は「粘り勝ちした」と思っているようです。ここまで落ちたけれど気持ちの切り替えができたって。それで、「受かるまでやるのが勝つ方法だ」なんて言い出して。それを見て、私も夫も大満足で受験を終えることができました。
編:不合格が続く中、Kさんはお子さんにどんな接し方を心がけていたのでしょうか。
K:6回も落ちるとさすがに言葉がなくなってくるのですが、子どもの前で私ががっかりしたり、「残念」という言葉をかけたりするのは絶対に良くないと思い、毅然としていました。それが本当に辛かったです。そんな中で、娘が息子に、「絶対大丈夫だから」って強く言葉をかけてくれたことに救われました。実際、息子がそれをどう感じたのかは分かりませんが、経験者の娘がかけてくれる言葉が、親の私たちを励ましてくれました。娘は受験中に親が忙しいことも理解してくれて、私たちが帰宅したら洗濯物を洗って畳むところまで終わらせてくれて、お味噌汁も作ってくれていて。1日、2日くらいのことでも、本当にうれしかったです。
オ:娘さんも息子さんも、中学受験を通して人間的な成長をされましたね。中学受験なんて、絶対にやらなくてはいけないことじゃない。でもせっかくするのだとしたら、目先の点数を上げるのではなくて、過酷な試練をどうやって人生の糧にしていくのかということがよっぽど大切です。お子さんたちが成長できたのは、親御さんがしっかりした価値観を持って、目先のことに振り回されなかったからだと思います。
編:第一志望に合格しなかった方から「受からせてあげられなかった」という言葉を聞く機会が少なくないように感じるのですが、Kさんはそういう感情にはならなかったですか?
K:それは受験当時も今も、全く思い浮かびませんでした。親がいくら「やらないと成果が出ないよ」と言っても、実体験として自分で学ばないと響きません。落ち込んで涙を流している息子のことを、もちろんかわいそうだとは思いましたが、どこかでこういう結果になるだろうとは予想していました。「勉強しなければ結果が出ない」ということを思い知ったのが、この12歳の今で良かったと感じています。中学受験を考える以前は、スイミングに通わせても「みんなバタフライまで進んでいるのに、なんでうちの子はまだクロールなの?」といったように、周りと比較してしまうこともありました。でも子どもを見ていたら、結果を求めたり、親がその結果に一喜一憂したりしていることが子どもにとってストレスになっているなと気づきました。
オ:親が「受からせてあげられなかった」と考えてしまうのは、やっぱりどこかで自分が子どもに与える影響力を過大評価しているのではないかと思うのです。それでは、子どもはいつまで経っても自分の人生を自分のものとは感じられません。「受からせてあげられなかった」と思うこと自体は、よくあること。仮にそう感じてしまう段階だったとしても、そこからだんだん親も成長していくのだと思います。Kさんはその段階をすでに超えていたから、最後まで粘り勝ちで摑んだ合格を家族全員で喜んで、笑顔で終わらせることができたのでしょうね。まさに中学受験の「必笑法」を体現されていると思います。いつも僕が言っている中学受験のあり方を証明してくれたようで、うれしいです。きっと皆さん前向きな気持ちで入学式を迎えられることでしょうね。
Profile

おおたとしまさ
教育ジャーナリスト。1973年東京都生まれ。東京外国語大学中退、上智大学英語学科卒。リクルートから独立後、育児・教育分野で活躍。執筆・講演活動を行う。著書は『なぜ中学受験するのか?』(光文社新書)など80冊以上。http://toshimasaota.jp/
イラスト/Jody Asano コーディネート/樋口可奈子 編集/水澤 薫