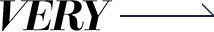【中学受験】打たれ弱い性格の小1長男、どんな塾にいつから通うべき?

『中学受験生を見守る最強メンタル!』というタイトルで書籍化された、話題の連載・おおたとしまささんの『悩めるママのための、受験進路相談室』。この連載では、過熱する都心部の中学受験や受験をとりまく環境に悩むママが毎月登場し、教育ジャーナリストのおおたとしまささんに進路相談。おおたさんの愛あるアドバイスは必読です!今回は、小学校1年生の息子さんの中学受験を見据えて今何を優先すべきか、さらに深い悩みも抱えているお母様からの相談です。
こちらの記事も読まれています
【今月の質問】
打たれ弱い息子、競争の多い中学受験にあたって
どんな塾にいつから通うのがいいのか小1の今から迷っています
[受験進路相談室]

Tさんの場合
【家族構成】
夫、長男(小1)
【今回相談する子どもの状況】
小1の息子に中学受験のための塾を始めさせるタイミングや、塾選びのポイントに悩んでいます。幼稚園から公文に通わせており、先に進みすぎてしまっているので、そろそろじっくり思考する時間を持ってほしく、知育教室に切り替えようと思っています。低学年のうちは知育教室、いずれ中学受験の専門塾に通わせたいです。夫は中学受験を経験しており、子どもにも受験させたいと考えているようです(私は経験なし)。また、夫は自分が講師としてアルバイトをした経験から、打たれ弱い息子には、クラス昇降が激しい塾は向いていないのではないか、と言っています。受験率が高く、塾が多数あるエリアに住んでいるので「この塾がいい」「複数見学してから決めるべき」「小2から通うのがいい」など、いろんな情報があり、よくわからなくなっています。また、私自身もインターネットで色々と調べるのが苦手で、すでに疲れてしまっています。
T(相談者):小1の息子がいます。夫は中学受験を経験しており、中学受験を見据えています。息子は年中から公文をやっています。いま小6の範囲まで進んでいます。公文をやっていることが本人の自信になっているようですが、だんだん負担も大きくなってきて、つらいと言い始めました。中学受験をするなら小6までの範囲を終えれば十分なので、思考力をメインにする教室に入りました。でも、つらいと言いながら、公文もまだ続けています。一方で、息子には打たれ弱い性質があって、中学受験塾に入ったら競争、競争という環境になってしまうと思うので、大丈夫かなという漠然とした不安があります。ですからいきなり小3に中学受験塾に入れるよりも、少しずつ慣らしていったりしたほうがいいのかとか、相談したいです。
お(おおたさん):まだ小1で具体的に何をするわけじゃないけれど、いまのうちからお母さんのなかで中学受験に対するビジョンをつくっていきたいということですよね。素晴らしい。
T:ありがとうございます。
お:まず、小1から中学受験塾に入れる必要はありません。これは中学受験関係者がみんな口をそろえることです。まあ、中学受験塾の低学年コースに入れてみたら、本人が楽しいと言ってハマったというのなら、通わせてあげればいいと思いますけど。
T:はい。
お:計算力を磨くだけじゃなくて思考力系の教室に通い始めたということですが、思考力養成をうたう教室はいろいろあって玉石混交かなという気はしますが、それも本人が楽しんでいるなら、いいんじゃないでしょうか。どこまで思考力が伸びるのかはわかりませんが。ご心配されているように、たしかに中学受験塾に通い出すと、それなりに忙しくはなります。でもそれもやり方次第です。どこまで追い込むかってことです。その子のペースでおおらかに頑張れる範囲で頑張って、それで合格できる学校に堂々と進学すればいいと思えるなら、中学受験をそんなに恐れることはありません。「せっかく塾に通ったのにあの程度の学校なのね」って心ないひとがささやいたりするわけだけど、そこをシャットアウトできる強さが親にあれば。SNSなんかを見ていると、トップアスリートみたいに極限まで追い込む中学受験が普通なのかなと思っちゃうかもしれないですけど、そんなことはありませんから安心してください。でも、お母さんご本人が中学受験を経験していないと、そこがいちばん不安なんですよね。肌感覚がないから。自分の無知や経験不足が原因で子どもを伸ばしきれなかったらいけないという恐怖に駆られてしまう。その恐怖から逃れるためにやらせすぎてしまうということがあります。
T:そうですね。はい。
お:中学受験の全体像としては、まずそこをお伝えしたくって。中学受験を見据えて低学年のうちに何をしておくべきですかという質問に答えるなら、低学年のいまだからこそ喜びを感じられる素朴な経験をたくさんさせてあげておいてくださいということです。近所の公園でチョウチョを追っかけているだけでも子どもには貴重な体験です。時間を忘れてしまうほど何かに夢中になれて、しあわせな気分に浸れるという、喜びの原体験を幼少期にたくさん積んでおくことが人生の土台になると思うので。中学受験を見据えているのならなおのこと、そこを大切にしてほしいと思います。
T:はい。
お:さきほど打たれ弱いから競争に晒されて大丈夫かとおっしゃっていましたけど、どうやって競争に振り回されないようにするかですよね。勉強ができないのを悪いことだと思い込まされて、恐怖を原動力として勉強を“自主的”に頑張る子もいるんです。それで第一志望に合格できても、自分はいつか転落するんじゃないかって常に不安です。人生がものすごくつらいものになってしまう。ひとと比べなくても自分は自分でいいんだと思える原体験を幼少期にどれだけ積んでいるかって、そういう意味でも大切だと思うんです。
T:いま体操教室にも通っているんですけど、上のクラスに上がったら、まわりができることを自分ができないことが増えて、悔しくて癇癪を起こしてしまうことがあります。それを見ているとこちらもつらくて。悔しがるのは悪くないし、いま挫ける体験をしたほうがいいと教室の先生も言ってくれているのですが、塾に行けば優秀な子がたくさんいるでしょうから、自分がまわりより劣っていると感じないのは難しいと思います。あの子の打たれ弱さに私がどう関わればいいのか、心構えを聞きたいです。
お:何かができるから偉いとか、ひとよりも上手だから偉いとか、そういうのじゃなくて、たとえば泥水の中に何度も飛び込むとか、大人から見たら無意味なことでも、それに夢中になって目を輝かせているあなたが素敵なんだよというメッセージを、つまりあなたが素直なあなたでいることがいちばん素敵なことなんだよ、それがいちばん嬉しいんだよと、親が心底思っていることが子どもに伝われば、子どもはものすごく安心できると思うんです。そういう土台があれば、挫けても立ち直れると思うんです。自分が祝福されて生きている実感を原体験としてもっているということです。
「あなたがあなたでいることがいちばん」と伝われば受験だけでない競争で挫けても立ち直れる子に
T:息子は頑固なところもあって、そこをほどいていく難しさも感じています。「なんで公文をやらされてるの?」と言うから「やめてもいいんだよ」と言うと、「やめるのも、お母さんたちが決めているんでしょ」って。「やめない」って、言い張ります。
お:へー。
T:中学受験についても、途中から「やらされている」って言い出すんじゃないかなって。中学受験をすることになっても、都度「本当にやりたいかどうか」を確認しないといけないと思うんですが、それでも「やらされている」という感覚をもたないで欲しいなと思ってしまって。公文については私も怒ってしまって、受け止めてあげることがまだできていなくて。
お:そこはどうなるかわからないじゃないですか。お母さんがそこに不安を感じてしまうのはなんでなんだろうな。
T:うーん、本当に子どもが望んでいることを選べないんじゃないかと思ってしまうんです。とりあえず親として、子どもがやりたいことを応援することしかできないと思うんです……すみません、涙が。「やらされている」って言い出したときに、子どもの本当の気持ちを、どう理解してあげられるかなと。
お:なるほど。いまも子どもの気持ちを本当に理解してあげられていないかなと、不安なんですね。
T:そうですね、受験ってなると、もっと同じようなことが起きるんじゃないかと思ってしまいまして。
お:いまの時点で、子どもにちゃんと寄り添えていないんじゃないかという不安がお母さんのなかにあるのなら、将来を心配するよりも、いま、その不安としっかり向き合うことが大事な気がします。
T:ピアノの練習も「したら?」って言うと、「なんでやらされなきゃいけないの?」って反発するし。「やりたくなければやらなくていいし、学校に行っているだけで十分だし」と言っても、どんどん口が達者になってきて喧嘩になります。打たれ弱さの部分についても、「自分だけできなかった」と癇癪を起こしているときに慰めても、それにかぶせて自己否定するような悲しくなるようなことを自分でどんどん言い出すので。最初の相談からだいぶズレてしまって、すみません。
お:いいえ。核心に迫っていると思います。公文は、自分の意思のないうちから親に連れて行かれて、やることが当たり前になっている。公文もある意味競争じゃないですか、進度があって。で、自分はそこでいい位置にいる。もしかしたらそのポジションが自分の価値だと思い込んでしまっていて、それを手放すことへの恐怖をもっているのかもしれない。お母さんも、何かねじれたものがあると感じていて、自分の責任と捉えているっていう可能性もあると感じたのですが。どう思います?
T:その通りだと思います。実際、生活の中心が公文になってしまったので、それを切り替えたくて。公文だけがすべてじゃないと本人には言っていて、実際に宿題がないほうが楽っていうのは本人もわかっているんですね。でもやらなきゃというのはすごく感じていて。進んでいるということに関しては、私と夫も「すごいじゃん」って言ってしまっているので、彼のなかでも褒められるからやりたいって思っているのかなと。同じことが受験でも起きてしまうんじゃないかって不安があります。
お:息子さんは公文を自分のアイデンティティの一部にしてしまっているんだと思うんですよ。よくいえば愛着、悪くいえば執着です。小学校3、4年生になればそれを切り離すことができるかもしれないけれど、まだ1年生だとその自己像ができていないから、それに困難を感じているというだけなんだと思うんです。公文をやったことが失敗じゃなくて、そこまでの価値になったのはいいことだと思う。それをどううまく卒業させてあげられるか。いまの状況で無理矢理引き剝がすのは得策ではない気がしてきました。毎日こなす枚数を減らしてみるとか、3カ月間だけお休みしてみるとか、ちょっとずつ距離を置きながら、「公文がなくても、あなたはあなただよ」と。さっきお母さんは息子さんの頑固さを「ほどく」という表現を使われたんですけど、頑固なら頑固さを楽しむという方法もあると思うんです。何かにこだわっていたら、そのこだわりをほどこうとするんじゃなくて、「どうしてそんなにこだわるのか教えて」というスタンスに出てみる。本当に興味をもって、息子さんの内面を探究してみる。そうすると、息子さんの本当の気持ちが表に出てきて、何かが変わるかもしれないという気がします。
T:そうですね、先ほどの「教えて」って一言、こんどタイミングがあれば、ぐっと堪えて、試してみます。
お:子どもに対して「なんでそんなことするの?」と思うとき、神様から自分への「さて問題です。いまこの子がこんなことをするのはなんでだと思う?」という問いかけだと捉え直すと、子育てって楽しくなりますよ。そういう経験をいまのうちにたくさん積んでおけば、中学受験で似たようなことが起きても、うまく対処できるようになっていると思います。
深くて複雑な相談でした。でも中学受験を始める前のこのタイミングでこの葛藤と向き合えることには大きな意味があると思います。
Profile

おおたとしまさ
教育ジャーナリスト。1973年東京都生まれ。東京外国語大学中退、上智大学英語学科卒。リクルートから独立後、育児・教育分野で活躍。執筆・講演活動を行う。著書は『なぜ中学受験するのか?』(光文社新書)など80冊以上。http://toshimasaota.jp/
イラスト/Jody Asano コーディネート/樋口可奈子 編集/水澤 薫