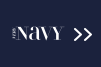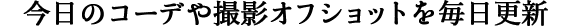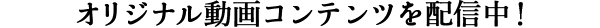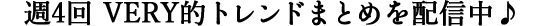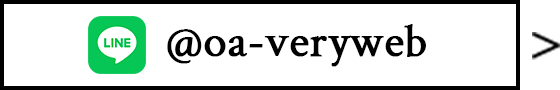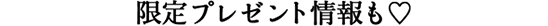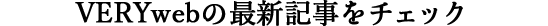才能を伸ばすのも、健康を守るのもここ次第?
子育て中のママなら誰もが気になる、子どもの能力や健康の“土台”作り。
何ごとも早期から!と闇雲に焦る必要はないけれど、ベストタイミングを知って意識すれば、もっと効果的に子どもの能力や健康を育てられるかもしれません!

歯や肌と同じくらい、ママの意識ひとつで未来が大きく変わる
脳も才能も育つ! 習いごとや習慣“始めるベストタイミング”の真実
脳の部位(能力の種類)によって発達のピークが異なります。脳の成長の特徴を知ることでわかる、子どもの成長過程に応じたベストな習慣や習いごとを教えてもらいました。




聞いたのは…
瀧 靖之教授
東北大学加齢医学研究所 教授・医師・医学博士。一児の父。著書に10万部を超えた『「賢い子」に育てる究極のコツ』他。
脳の成長の特徴を知れば、いつ何を始めるべきか、が明確に見えてきます
我が子のさまざまな可能性に期待し、幼少期から幅広い習いごとをさせたくなるのが親心ですが、脳の成長の特徴を知れば、もっと効率良くその能力を伸ばすことも可能です。というのも、脳の複数ある領域はそれぞれ発達する時期が異なり、習いごとを始めるならそれに関連したものを適切なタイミングで始めるのが最も効率的なのです。例えば生後すぐに発達するのが、ものを見る機能を担う「後頭葉」。この時期は視覚を刺激するため、小さな赤ちゃんにまずしてあげたいのは、絵本や図鑑を読み聞かせたり見せてあげること。3〜5歳は運動や音楽にまつわる習いごとを。この2つを司るのは「運動野」という領域で、大人になってから運動神経の良い人は、その多くが幼少期ピアノを習っていたというデータも。特に早期教育を実践する家庭が多い英語は、8〜10歳頃が最も効率的に習得できる時期。10歳以降はコミュニケーション力が高まる時期なので、学校の部活をやらせるのも有効です。また年齢にかかわらず、脳の成長にとって不可欠な栄養となるのが好奇心。親が子どもの頃からさまざまなものを見せ、触れさせることが重要と言えます。
子どもの目の健康だって、意識を向けるべきベストタイミングがある!
虫歯と同じように、近頃は親の心がけ次第で防いだり進行を遅らせることができるとわかってきたのが「近視」。年齢ごとに、親が気をつけてあげられることがたくさんありました。

両親とも近視なのですが、0歳の息子に気をつけてあげることはありますか?
0歳児ママ/金 奈民さん (35歳) 長男5歳、次男0歳7カ月

寝るときは昼寝も含め真っ暗な環境を徹底
近視は遺伝の影響が大きいだけでなく、環境も大きな要因となるので、家庭での心がけ次第で改善できることも。まず赤ちゃんが眠るときは、昼寝であっても遮光し、真っ暗な環境を作ること。明るいと目を閉じていてもボヤッとしたピントの合わない残像が網膜に映り、ピントを合わせようと眼球が伸びるため、この状態が結果的に近視のリスクを高めるという説があります。
※現状は仮説としての内容です。エビデンスについての研究は現在進行中


外出し一日2時間程度太陽光を浴びる習慣を
日常的に外出をする年齢になったら、目の健康のためには毎日約2時間、外で過ごし太陽光を浴びるのが理想。太陽光に含まれる「バイオレットライト」は近視抑制作用が期待されている光。屋内ではほとんどの窓ガラスがUVとともにバイオレットライトもカットしてしまうので、紫外線対策を万全にしつつ積極的に外出を!


近くを見る作業は長時間続かないよう注意
絵本を読んだりお絵かきをしだしたら、作業は極力場所を決め、正しい姿勢で30分を目安に、をこの時期にぜひ習慣づけて。定期的に近くから目が離せるよう外で読書をしたり、あえて使う道具を不便なところに置いてみるのも手。また寝かしつけるとき薄暗いところでの読み聞かせも近視の原因に。目をつぶらせて、音だけを聞かせてあげるのが理想です。


3歳になりiPadやテレビにも興味が出始め、目への影響が気になっています。
3歳児ママ/保谷絢子さん(35歳) 長男3歳

疾患の早期発見にも繋がる3歳児健診は必須
幼児は視力が低下していても不自由なく、見えにくさを訴えることがないため、親も気づかないことが多いものですが、幼児の近視が増えているため必ず自治体の3歳児健診を受けて。送られてきたキットを使い、家庭で簡単な一次検査をしたのち、必要に応じて二次検査、眼科の精密検査を。弱視や斜視などの早期発見に繋がることもあるので、ぜひ忘れずに。


就学前健診で近視と診断されました。普段の生活で心がけるべきことは?
6歳児ママ/平田沙耶華さん(35歳)長女10歳、長男7歳、次男5歳

近視の場合はすぐに処方箋で適切なメガネを
就学前健診で視力に異変があれば、眼科で処方箋をもらってメガネを。見えないのに裸眼で過ごすと、遠くにピントを合わせようと眼球が伸び、近視をさらに悪化させます。また子どもは近くを見る「近業」が続いても疲れたという自覚症状が出にくいので、親が意識することが大事。近くにも遠くにもピントが合う遠近両用レンズという手も。バイオレットライトを通すレンズをオプションでつけるのも◎。
メガネ:上(KRF-16A-348 34)¥5,000 下(KRF-16A-347 76)¥5,000(ともにJINS)

中学生はコンタクト+メガネで近視の進行抑制を
近視の場合は、自分自身で管理ができる中学生以降、調節緊張をやわらげるために遠近両用のコンタクトレンズを取り入れても。ただしコンタクトだけでは目に負担がかかる可能性があるので、必ず帰宅したらメガネに切り替え、併用することが大切です。近視が進行するのは18歳頃までと言われているので、抑制の対策をするならこれまでの時期に行うことが重要と言えます。
聞いたのは…
石川まり子先生
田園調布眼科院長、田園調布小学校校医、めぐみ幼稚園園医
0歳から始められる〝眼球を伸ばさない〞生活で近視から子どもの目を守って
子どもの近視は重大な病気ではない、と考えている子育て世代も多いですが、小学生や未就学時から近視がスタートすると、目の構造が出来上がる18歳頃までに強度近視に進行する可能性が高いので、発症を未然に防ぐこと、なったら進行を遅らせることが重要です。まず子どもが近視と診断された場合は、すぐに眼科を受診し、処方箋をもらいメガネを作って。見えづらいのに遠くを見ると、目がピントを合わせようと眼球を伸ばしますが、この状態は近視を進ませるだけでなく、網膜剝離や緑内障などさまざまな重大な疾患の原因になる可能性が。最初はピントの調節による一時的な仮性近視(調節緊張)ですが、この状態が続くとやがて本当の近視に発展するので、上の表のような眼球を伸ばさない生活習慣を徹底することと、近視抑制に効果があると期待されているバイオレットライトを屋外でなるべく浴びることが大切。幼少期の視力の低下は親でも気づきづらいので、小さな変化を見逃さないことが子どもの目の健康において重要な鍵を握っています。
お問合わせ先/JINSカスタマーサポートセンター 0120-588-418 https://www.jins.com/jp
イラスト/CHINATSU 取材・文/沼田珠実 デザイン/平岡規子