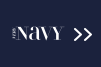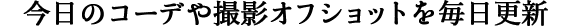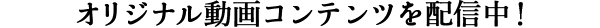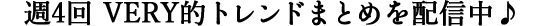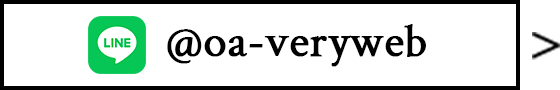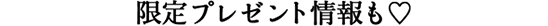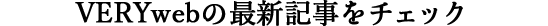「お金ってなんで必要なの?」何気ない子どもの質問に、ドキッとしたことがあるママたちに向けて。社会的金融教育家・田内学さんの連載が復活!今回は、「おこづかいって意味あるの?」と悩むママの疑問にお答えします。
こちらの記事も読まれています
元GS、社会的金融教育家・田内 学さんが回答!
ママのための「お金の教育」
悩み相談室
今月の戸惑うママ
Kさん(30代・共働き、小2女のコママ)
自営業の夫と結婚以来、専業主婦として現在小2の女の子の育児に奔走。昨年自身もフリーランスとして仕事を再開したママ。
お金の管理を学ぶのならもちろん意味アリ。
「価値」を学ぶなら、日々対話しかない
田内学さん(以下、田内) Kさんは「おこづかいって意味あるの?」と悩まれているということですが娘さん自身は、おこづかいを欲しがっているのでしょうか。
読者 Kさん(以下、K) 本人からのリクエストはまだありません。ただ、娘はお買物が好きなんです。それも高いものではなく、ちょっとしたものがすぐ欲しくなるタイプで、ガチャガチャも大好き。今の娘にとってのワンダーランドは100円ショップで、かわいいファイルや工作用のレジン液などをすぐ買いたがります。ガチャガチャなどは特別なときに1回だけと約束していますが、工作を楽しむのは悪いことではないし、お友だちへのプレゼント用ラッピングが必要と言われればつい買ってあげてしまいます。納得できる使い道なら親が出してあげてもOKという状況で、どこからどこまでが自分のおこづかいで買うべき範疇なのかを決めるのが難しくて。仮に500円と決めても、あっという間になし崩しになりそうで、おこづかい制に踏み切れません。
田内 私も親として共感する部分が多い話です。我が家はおこづかいとは別に、交通費をICカードにチャージしてあげています。塾の前にお腹が空いたらそれで何か買って食べることもあるようです。そう考えると、塾の前に食べるなら親が出してあげるけれど、友だちと寄り道して食べるなら自分のおこづかいから出しなさい、というのも変な話ですよね。どちらも同じ食べ物なのに…。おこづかいって意味がない、というのが今回の結論かも(笑)。ただ、子どもにとっては、「お金にも制約があるという概念」を学ぶことは意味があるかもしれません。Kさんご夫婦はそれぞれおこづかい制ですか?
K うちはそれぞれが自由に使っています。少し前までは専業主婦で、収入源は夫のみだったので、洋服なども家計から買っていました。高額なものはお互いに相談するようにしています。
田内 夫婦の間では、「これは使ってもいい」「これはさすがに使わないほうがいい」という暗黙の了解が通用するけれど、これを子どもとは共有できないから難しいのかもしれません。例えば、親に出してもらうなら親を納得させる理由が必要だけれど、本人のおこづかいなら使い道は自由ということであれば、裁量権を持つという意味でおこづかい制が生きてくるとも言えます。
K それはまだ娘には難しいかも。おこづかいを月の前半に使い切ってしまって、残りの半月を我慢できなくなってねだってきそう…と思ったのですが、そういえば先日娘と韓国に行ってきたんです。お買物をしたがったので、シールや文房具を買うための予算をあらかじめ渡して、自分で調整して使ってねと伝えました。そうしたら旅の終盤に行った店で、予算ギリギリ2,000円くらいのネイルチップが欲しくなってしまったんです。明日もお買物をしたいからどうしよう…と悩みに悩んで買い、いまだにそのネイルチップはとても大事にしています。結局、翌日にまた欲しいものが見つかってしまって私がお金を出してあげたのですが、それでもいい経験をさせてあげられたと思いました。毎日こうやって予算管理するのは大変かもしれないですが、旅先で期間限定だったからできたのかもしれません。

限りあるおこづかいを前に、
必死で考える
田内 どうせ親が出してくれるからと思ってしまうと、いつまでもコスト意識は持てません。お子さんはネイルチップを買う前に、「この2,000円を今使わなかったら次の日に何が買えるだろう」と必死に考えたうえで選択したのでしょうね。どこまでがおこづかいで、どこからが親が出してもいいかという線引きで迷う人も少なくないと思うのですが、その裏には「学びの要素を持たせたい」という親の思いがあるからのような気もします。学校や塾は学びの時間と休憩時間との線引きがあるけれど、家庭では学びの時間と一緒に楽しむ時間との線引きがきれいに引けないので。お金の管理を学ばせたいなら、Kさんがすでにやったように旅行や夏休みなど、期間を区切っておこづかいをあげてみるのも一つの手。でもお金の価値観を学んでほしいのだとしたら、「お母さんはガチャガチャを一日に何度もやるのはもったいないと思う」という気持ちを伝えてもいいと思います。
K では我が家はまず、旅行のときのお土産代として、予算を決めておこづかいをあげるところから始めてみようと思います。お金の価値観に関しては、すでに懸念していることがあって。娘は私立小に通っているのですが、附属の中学校に上の子を通わせているママ友から「クラスメイトと月に1回某テーマパークに行くのでお金がかかる」という話を聞きました。それなりにゆとりのあるご家庭で、お子さんも自分の家の経済状況を理解しているだけに、「お金がないから行っちゃダメ」とは言えないらしいんです。我が家も今の時点でお友だち母子と新大久保やモールに買物に行く機会が多く、「友だちと同じものを買ってほしい」と言われると、これ以上は出せないと言えず。お付き合いもあるので、覚悟を決めて財布の紐を緩めています。この先、中学生になって「遊園地に行きたい」とか「おこづかいをもっと欲しい」と言われることも出てくると思うと、娘にお金の大切さについてもっと深いところから教えていかないといけないと感じています。
田内 これまでの連載ではなかなか踏み込めなかったのですが、相談者さんのお悩みの多くは大きく3つの要素が絡み合っているように感じます。①子どもの金銭感覚がこのままだとまずいのではないかという心配。②お金を出さないことで、子どもにケチだと思われる、嫌われてしまうのが怖いという気持ち。③周囲と比較してそこまでお金に余裕がないことを、はっきり子どもに伝えられないという本音。①の割合が強いけれど③もあるという場合や、②と③が半々ということもあるでしょうが、この3つが悩みのほとんどを占めている気がします。
K そう言われてみると、①の割合はかなり大きいです。②と③は自分ではそんなに感じていなかったのですが…もしかしたら、④として、「お付き合いを大事にしたい」というのが挙げられるかもしれません。一緒にお買物に行くママ友たちのご家庭とは金銭感覚も経済状況も違うのですが、我が家が買うか買わないかを迷うことで時間を無駄にさせたくないと思ってしまいます。でも、決して無理して合わせているわけではなくて、娘が大好きなお友だちと楽しい時間を過ごすことが大事だと思うからお金を使っているという感覚があります。ただ、毎回お付き合いするのはさすがに厳しくて、数回に1回は断ることもあります。行けるときは思いっきり楽しもうと思っているのですが、娘がそれは特別なことであるのを理解してくれているのかどうか…。娘も大きくなったら、自分の状況を見ながらお付き合いする、しないという判断ができるようになってくれたらいいのですが。
娘が将来、自分と同じように
暮らしていける保証はないから…
田内 なるほど。親ががんばってお金を出していることを、子どもは分かっているのだろうか、という葛藤もありますよね。お金に対する考え方について、何が間違っているとかどれを解決しなければいけないということはありません。自分の悩みは①~④のどれが強いのか、優先して考えるべきなのはどれかを自分で整理するだけで、少しラクになれるような気がします。Kさんは①子どもの金銭感覚と④お付き合いを大事にしたいという点で悩んでいた自分にも気づけたわけですし、④に関してはすでにそれなりの折り合いがついているということですよね。夫婦でも金銭感覚が合わないこともありますが、夫婦はその都度話し合っていけばいい。でも子どもは自分たちより圧倒的に長く生きるので、いつまでも助言し続けるわけにはいきません。子どもへのお金の心配は尽きなくて当たり前だと思っていてもいいと思います。
K 子どもの将来が心配という話で言うと、あるご家庭のお金に関する話を聞いて感心したことがありました。かなりゆとりがある経営者のご家庭なのですが、食費などの生活費はきっちり予算を決めて管理しているそうです。子どもたちが将来自分たちのような生活を送っていける保証はないからと、夫婦で話し合って、きちんとした金銭感覚を身につけさせようと決めたらしいんです。うちは大金持ちではないけれど、今の時代に東京で子育てできている時点で恵まれていると思います。でも、娘が将来同じような状況で生活していけるかは分かりません。そう考えると、地に足のついた生活を知ってもらうことも大事だと感じています。
田内 そうか、自分が暮らしている中で「お金に余裕がない」と言い出しにくい雰囲気になってきたような感覚がありましたが、今回のお話でその理由が少し分かったような気がします。
K それもあって、「お金がないから」と諦めさせるのは違うような気がしていたんです。私自身、何に悩んでどう対処していくべきかという優先順位も見えてきたので、これからの子どもへの教育に生かしていきたいと思います。あとはやっぱり、親ががんばっていることは分かってもらいたいので、時に悩みながらお金を払っている背中を見てもらえたら(笑)。今はまだ理解できないと思いますが、中学生になったら「ママががんばって働いたから、このお金で遊園地行っておいで」と言えるようになってみたいです。

田内学さん
1978年、兵庫県生まれ。2001年、東京大学工学部卒業。2003年、同大学院情報理工学系研究科修士課程修了後、ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーダーに。2019年に退職後は、子育てのかたわら、金融教育家として講演や執筆活動を行っている。インスタグラム@tauchimnbで経済やお金の情報を発信中。

『きみのお金は誰のため
ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』
田内 学著¥1,650/東洋経済新報社
中2の優斗はひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海と謎めいた屋敷へ。そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり「お金の『3つの謎』を解けた人に屋敷を渡す」と告げられる。大人も子どもも一緒に読みたいお金の教養小説。
撮影/吉澤健太 イラスト/犬ん子 取材・文/樋口可奈子 編集/中台麻理恵
*VERY2025年8月号「ママのためのお金の教育悩み相談室」より。
*掲載中の情報は誌面掲載時のものです。