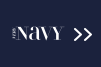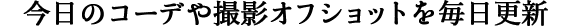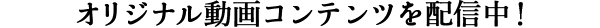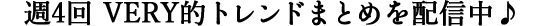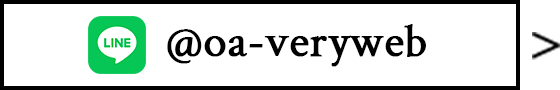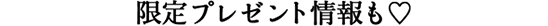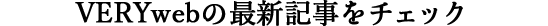子育てや家事は一人で抱え込まず、家族や友人、行政、家事代行サービスなど頼れる先に頼ればいいと頭ではわかっていても、“ひとに頼ること”に罪悪感を抱くママは少なくありません。そこで京都大学大学院教授・柴田悠先生と2児の母でVERYモデル・笹川友里さんが対談。「家事代行は手抜きではなく、誰もが使える社会のインフラ」という視点から、いま必要な【受援力】について語り合っていただきました。
VERY読者、チームVERYに聞いた
家事支援サービスを使ったことはある?

缶の分別や洗剤の詰め替えなど「名もなき家事」を週一でシルバー人材センターに依頼。掃除は得意だけれど、タスクが減り精神が安定。今はなくてはならない「お守り」です。
(5歳女の子ママ・竹中紘子さん)

家事代行サービスを申し込んだら、夫に「家に人を上げないで」と言われ泣く泣くキャンセル。ひざを突き合わせての話し合いが必要だなと思いました…。
(4歳、2歳男の子ママ・森 沙保里さん)

2人目育休中のいま、宅食サービスを利用中。料理へ割く手間と時間が減ったことで気持ちの余裕が生まれ、ひたすら0歳を愛でることができ、3歳の上の子にも優しく接することができています。
(3歳、0歳ママ・菅原南美さん)
頼ることは弱さじゃない、
家族や社会を守る「強さ」になる

(左)笹川友里さん (右)柴田悠先生
編集部
笹川さんは現在6歳、2歳の2人のお子さんのママ。第1子を出産した当時と比べて、子育てのスタイルはどう変わりましたか?
笹川
最初の子のときは、とにかく「私が全部やらなくちゃ」と思い込んでいました。母が専業主婦だったので、自分もそうすべきだと無意識に決めつけていたんですね。なので外に頼るなんて発想はまるでなく、全部一人で抱え込んでいました。
編集部
今では家事代行やシッターも頼んでいると伺いました。きっかけは?
笹川
夫です。第1子出産後、「一度頼んでみよう」と言ってくれて。ただ最初は抵抗がありました。お金を払っているのに「甘えている」みたいな気がして…。でも一度お願いしたら「こんなに楽になるんだ!」と驚いて。週に1回、2時間来てもらえるだけで余裕が生まれるのを実感しましたし、気づいていないだけで、“目の前にいるこの子をひとりで見なければ” と、それまで相当、気が張り詰めていたことに気づきました。頼ってみたら、子どもにも優しくできるし、家庭全体の雰囲気も良くなって。もっと早く頼めばよかったなと思いました。
編集部
笹川さんのように、家事育児をまわりに頼ることへの抵抗感があるという話は読者の方からもよく聞くのですが…。
柴田先生
とても多いですね。戦後の日本では「専業主婦+核家族」という体制が一般的になり、そのなかで母親が家事も育児も担うという価値観が広がりました。そうした経緯から、母親が家事育児をやることが美徳と考えられてきたのです。でも、人類の歴史をたどれば本来は村全体で子どもたちを育ててきました。人間の子どもはとても未熟な状態で生まれ、25歳くらいまで脳は発達を続けます。一人の親が抱え込むのは不可能に近い。育児や家事をひとりで担うのは、そもそも人類史的に不自然なんですね。我が家も、夫婦のどちらかが夜にいないときは、双子育児でシッターを頼りました。親1人で子2人をお風呂に入れるのはとても不安だったので、外部の力を借りるのは必然でした。
今の私たちに必要なのは、助けてほしいと言える「受援力」
笹川
ただ、最初の一歩がなかなか踏み出せないんですよね。
柴田先生
そうなんです。一回でも頼むと「なぜもっと早く利用しなかったんだろう」と思えるはず、と経験者としてお伝えしたいですね。助けてほしいときに「助けて」と言える力のことを最近よく「受援(じゅえん)力」と言います。これがないと、人は抱え込みすぎて潰れてしまうんです。
編集部
笹川さんの「甘えていると思って頼めなかった」という気持ちも、受援力が足りなかったからなのでしょうか?
柴田先生
そうですね。でも体験を通じて「頼ることは悪くない」と気づけた。それは受援力が育った瞬間です。

笹川
本当にそう思います。2人目の育児では、「母じゃなきゃ」と思いすぎず、ばぁばや友人の手を借りるようになりました。子どもにとっても多様な愛情を受けることはむしろプラス、と実感しています。
柴田先生
もうひとつお伝えしたいのですが、子どもの発達に与える家庭の影響は実は思っているほど大きくないと言われています。知的能力や協調性などの非認知能力の大部分は、遺伝や学校・友人といった「家庭外」の環境で決まります。だから「親がしてあげられることは無限にある」と思い込むと、かえって親が苦しくなるのです。
編集部
では親は何を頑張ればいいのでしょうか?
柴田先生
一番大事なのは、虐待やネグレクトをしないこと。 子どもに過剰な教育を与えるよりも、「叩かない」「無視しない」「感情に共感的に反応してあげる」ことの方がはるかに大事です。親がすべてを背負い込んで頑張る必要はない。むしろ頑張りすぎて余裕をなくす方が危険です。
笹川
これ、ママたちにとっては励みになる情報だと思います。「やってはいけないことをちゃんと避ける」ことは、大切なんですね。

柴田先生
親ができるのは、安全で安心できる環境を守ること。その上で、子どもが外の世界で多様な経験や人間関係に触れることの方が発達には大きく寄与します。だから親は「完璧にやらなきゃ」と気負う必要はないんです。
笹川
社会全体にも、「頼れる環境」がもっと広がるといいですよね。家事代行サービスの広告も「働くママが頼むもの」という色合いが強いと感じることがありますし、専業主婦が家事代行を頼むと手抜きと思われがちな気がして…。でも実際は誰でも使っていいものだし、家事代行をママ以外がマネジメントしても当然いいはず。
柴田先生
そこ、すごく大事です。例えば夫から「今日はシッターをお願いしよう」「家事代行を頼もう」「発注しておくね」と言わないと、いつまでも女性だけに負担が偏ってしまいます。
家事代行は“手抜き”じゃない。
誰が頼んでもいい、社会のインフラ

笹川
でも考えてみれば、たとえば仕事である一部を誰かに外注するのは普通なのに、家事や育児を外に頼むのは「母親の怠慢」みたいに見られるのは不思議。パパが率先して頼むことが増えれば、「家庭のことは夫婦どちらの責任でもある」という妻側へのメッセージになるだけでなく、社会全体の空気も変わりそうです。
柴田先生
そうですね、それにそもそも子どもがいない家庭や一人暮らしだって使っていい。家事代行は「特別な人のサービス」ではなく、社会のインフラなんです。頼ることは贅沢ではなく、生き延びるために必要な力です。そして、親が「助けてほしい」と言える姿を見せることが、子どもにとって最高の教育にもなります。受援力は未来の世代につながる力だと思います。
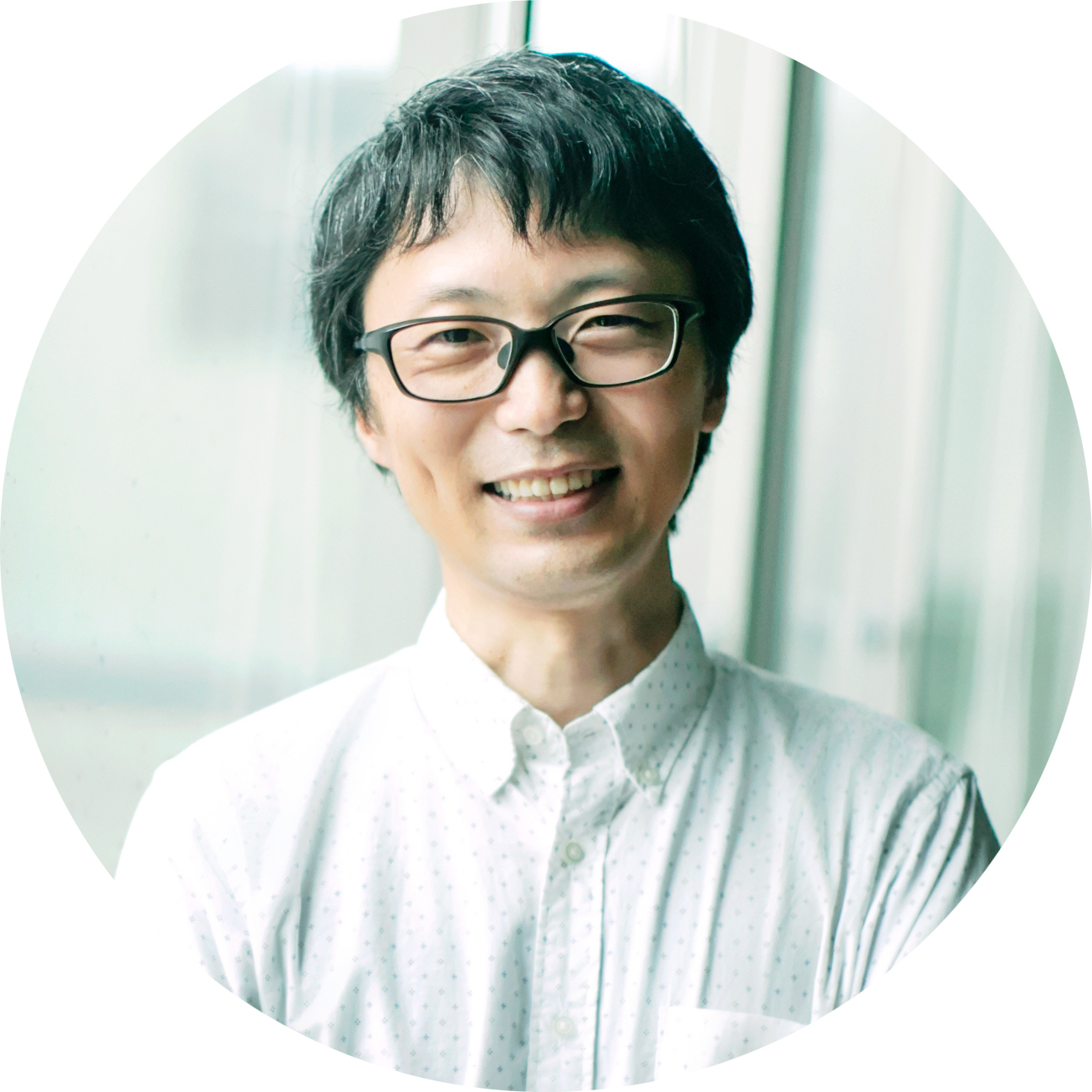
柴田 悠(はるか)さん
京都大学大学院教授。専門は社会学・家族政策。双子を含む3児の父でもあり、研究と実生活の両面から子育て支援や「受援力」の重要性を発信。

笹川友里さん
元TBSアナウンサー、VERYモデル。現在は2児の母として育児に奮闘しながら、執筆や講演など幅広く活動。2023年に女性のキャリア支援会社を創業、CCOを務めるなど幅広く活動。
PR・お問合わせ先/経済産業省
笹川さん分/ジャケット¥75,900ビスチェ¥46,200パンツ¥49,500(すべてSov./フィルム)Tシャツ¥16,500(ハイク/ボウルズ)ピアス¥88,000〈モニス〉バングル¥6,330〈エイチアッシュ〉(ともにフォーティーン ショールーム)パンプス¥39,600(ファビオ ルスコーニ/伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴)
撮影/須藤敬一 スタイリング/石関靖子 ヘア・メーク/只友謙也〈Linx〉 取材・文/有馬美穂 編集/中台麻理恵