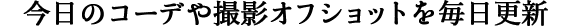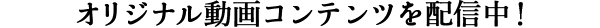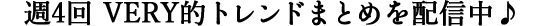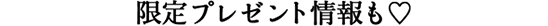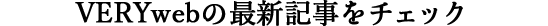「実はオトナも本当は、
そんなに強くはないのよ」
by リンゴ
聞こえてくる子どもたちの話し声に、ついつい耳を澄ましてしまう。あ、子どもたち、なんて呼んだら彼女たちに失礼ね。椅子に座り直しながら、すぐにそう思い直す。
私の背中の後ろ、一枚の布で仕切られたベッドに寝ているのは、6年生の女子二人。ちょくちょくここに眠りにくる雨川さんと、初めてここにきた泣き顔の鈴木さん。
どうして泣いているのか。もちろん気になった。でも、すぐに聞くのは違うと感じて二人をベッドへと通した。
正解だった。
「心が痛い時も熱がある時と同じように保健室を利用していいと、母から聞きました」と初めて会った雨川さんに言われた時から感じていたけれど、彼女は独特の世界を持っている。
奇跡という下の名前がピッタリすぎてびっくりする。娘をそう名づけたご両親も素敵な人だということが、彼女を見ればすぐにわかる。
いつもは「キキ」、「アミ」と互いを呼び合う親友同士の竹永さんと連れ添ってくることが多いけど、今日一緒にきた鈴木さんは二人とは雰囲気が違う。とても大人しそうな女の子。
「雨川さんは友達もいっぱいいるから、私の気持ちはわからない」と話す鈴木さんに、「友達はいても、本当の居場所は学校の中にはない」と答える雨川さん。
なんて深い会話をしているのだろう。盗み聞きをしたいわけではないのに、耳が離せなくなる。子どもなのにスゴい!とは思わない。子どもを下に見る大人たちの方こそ、なにもわかっていないのだ。
二人はすでに、とても魅力的なレディたち。
保健室の先生としてこの小学校にきてまだ2ヶ月だけど、私はすでにここでの仕事を愛しはじめている。子どもたちの魅力と果てしない可能性に、胸がいっぱいになるからだ。
あ。「子ども」とは呼ばれたくない妙齢の少女たちの気持ちもわかるけれど、やはり「子ども」とは素敵な存在。今でもとっても魅力的なのに、さらに進化する可能性が無限大に広がっているのだから!
これは、もうすっかりオトナになった今だからこそわかること。自分はもう、逆立ちしたって「子ども」には戻れない。そうなって初めて見えてくる。「少女時代」というかけがえのない時期の特別さが!
今すぐにでも仕切りのカーテンをめくって伝えたくなるけれど、彼女たちは同じ年だからこそできる会話を続けている。
—————「オトナになんか、なりたくない」、「子どもでなんか、いたくない」。
二人がそう言い合うのを聞いて胸がソワソワしはじめた。
反対のことを言っているようで、
共通点は一つ。
二人とも「今」が、苦しいのね。
そんな二人に伝えたいことがある。と、思ったけれど、先生になった今でも、私は女子同士の会話に自分から入っていくのが少し怖い。
それは、小学生時代の悲しい思い出と関係している。
あぁ、そうよね、とザワザワする胸で思う。「子ども」でいられる時期は特別だと大人になった今思うのも本当。でも、小学校の中に小学生として生きていたあの頃、たしかに私も苦しかった。
「オトナになりたくない」どころか「もう朝がこなければいいのに」。
そう思って夜に枕を濡らした夜が、私にも何度もある。父と母にバレないように、声を殺して泣いた。学校に行きたくなかった。だけど親に心配をかけることも、心配をされることもイヤだった。
頭の中にあるのは、イヤな気持ちのシーソーだった。学校に行くのがイヤ。でも学校に行かないことで親に心配されるのもイヤ。どちらのイヤが強いかどうか。私は、ものすごくイヤな学校に通うほうを毎朝選んでいた。
本当は夜だけじゃなくて、
昼間のほうが泣きたかった。
だけど歯を食いしばった。本当の気持ちなんか、大人には話せなかった。親にも先生にも。大人だけ? ううん、誰にも言えなかった。うん、あの頃、苦しすぎた。
「今」が辛いのに「未来」が明るいとは思えない。「オトナになんかなりたくない」、「もういなくなってしまいたい」という気持ちのルーツは、そういうことだ。30分ほど前に保健室に入ってきた時の鈴木さんの泣き顔を思い出す。
気持ち、わかる。
座っていた椅子から、私は立ち上がっていた。二人と話をするために。
これが私の「先生になった理由」なのだ。悩んでいる子どもたちの気持ちがわかるのは、私も悩んでいる子どもだったことがあるから。一人で泣いていたあの頃に、自分が出会いたかった大人になるために私はここにきたのだった!
「……」
立ち上がったものの、話しかける勇気が少し足りずに止まっている。布の奥、すぐ向こうのベッドに寝ている雨川さんも鈴木さんも、想像すらしていないだろう。
二人に話しかけることに緊張した私が、棒みたいにここに突っ立っているなんて。先生なのに! 大人なのに!
マヌケすぎて、笑っちゃうよね。
だけどそれも、伝えたいことのひとつ。相手が子どもであっても、生徒であっても、誰かに自分から歩み寄る時に勇気が必要な大人もいるってこと。もちろん人にもよるけれど。
大人だって先生だって、
実はそんなに強くないってこと。
そんなことを考えていたら、目の前の布がパッと開いた。
「わッ! 先生!! ビックリしたーーーッ!!」
真正面に私がいたことに驚いた雨川さんの声に、こちらの心臓も止まりそうになった。
「ご、ごめんなさい、驚かせちゃって」
胸を押さえながら伝えると、雨川さんは「あのね、スズが少し眠りたいみたいだから」と小さな声で言う。
私は頷き、鈴木さんが眠っているベッドの前のカーテンを閉める。
「なにか、あったのね? 泣くようなことが」
机に戻って腰を下ろし、雨川さんが座るための椅子を差し出してから聞いてみた。
「はい。でも、スズの涙の理由は聞いていないです。本人が話したくないことを無理に話させることって、愛じゃないし」
目の前に座ってそう語る雨川さんは、優しい目をしている。
「……素敵な言葉を話すのね。大人よりも大人っぽいくらいに。もちろんとてもいい意味で」
「嬉しいです。ありがとう。ね、先生、それホクロ?」
「え?」
雨川さんが、ジッと私の顔を覗き込んでいる。
「口元にホクロ。それも、椎名林檎と同じ場所! 私、ちょうどさっきの授業中、椎名林檎みたいな女の先生に恋愛について教えてもらいたいって思っていたから、ビックリ!! 」
「ええッ!? 」
思ってもみなかったことを言われて、「え」しか言葉が出てこない。
「恋バナとか、教えて欲しいな、先生の。初めてのキスとか、そういう話」
「わ、私の?」
言いながら、調子が狂う。私、完全に雨川さんのペースに呑まれている。
「今ここで経験があるのって先生しかいない。ねぇ、大人って楽しい?」
「う、うん。そうね、うん。楽しい! だけど実はオトナも本当は、そんなに強くはないのよ」
「わ、そっか。勉強になる。だって、それを覚えておくことで、私これからママの嫌いなところとかも、少しは許してあげられそう!」
そう言ってもらえて、なんだかホッとした。私たちは目を合わせて微笑み合った。すると、雨川さんの向こうでカーテンがスーッと開く。
「あの、すみません」
さっきの私みたいに、雨川さんとの会話をベッドの中から聞いていたのだろうか。「先生」と私を呼ぶ、鈴木さんの声がする。
「涙の理由、話したいです。聞いてもらいたいです」
<つづく>


作家。1981年生まれ。ニューヨーク、フロリダでの海外生活を経て、上智大学卒。25歳でデビュー以降、赤裸々な本音が女性から圧倒的な支持を得て著作多数。作詞やドラマ脚本も手がける。最新刊は『目を隠して、オトナのはなし』(宝島社)。8歳の長男、6歳の長女のママ。
Instagram: @lilylilylilycom