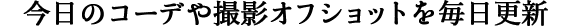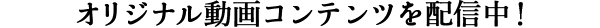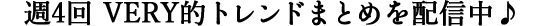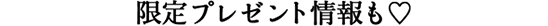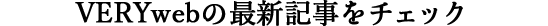「オトナになんか、なりたくない……」
by スズ
「このカーテン、ちょっとお姫様ベッドっぽくない? そこがね、好きなの、保健室」
ベッドとベッドの間を仕切る布を少しめくって、隣で寝ている雨川さんが小さな声で私に言う。昨夜からずっと泣いていたから、雨川さんの方に視線を向けるだけでまぶたが熱くて重い。
「真っ赤よ、目」
言われてしまって恥ずかしくて、逃げるように視線をまた天井に戻す。みるみるうちに目に溜まった涙が、顔の両端へと落ちていく。耳の穴の中まで濡れたのがわかる。だけど拭う元気ももうなくて、重たいまぶたが自然と閉じる。溜まっていた涙が、また同じルートを流れてく。
「泣くのって、気持ちいいよね。キスと、どっちが気持ちいいんだろう。鈴木さんは、どう思う?」
ビックリして目が開いた。雨川さんのそのうっとりしたような声も、言っている意味も、私にはまったくわからなくって、涙が止まる。「え?」。聞き返したつもりが声にもならない。
そもそも雨川さんは、私とはまったく違うタイプの人間なのだ。今まで話したこともなかったし、学年の中でも一番くらいに目立っている雨川さんのことを私はもちろん知っていたけれど、雨川さんが私の存在に気づいているかも疑問だった。
「鈴木さん、って言いにくいな。スズって呼んでもいい? 」
キス。スズ。泣くことは気持ちがいい。
頭がグルグルまわる。胸がドキドキしてる。
ううん、授業中に雨川さんから紙を渡された時からずっと心がソワソワと揺れていた。でも今は、自分の心臓がドクドクと脈打つ音が体の奥から聞こえてくる。
「あ、もちろん悲しいから泣くんだけど、泣いているうちにきもちよくなってくる時ない?」
私の返事を待たずに雨川さんは話し続ける。
「たぶんあれ、ね。身体の中から悲しい気持ちを、涙を使って外にどんどん出すからだよね。悪いことじゃないのよ、だから泣くって。スズも大丈夫よ、だから。泣きたいだけ泣いていいよ。そのための保健室よ」
止まったはずの涙が、また目から溢れ出す。だけどさっきとは、涙の種類が変わったことが自分でわかる。
「うんうん、泣きな泣きな」
雨川さんの優しい声がする。私は今、両手で顔を覆って泣いている。声が出てしまいそうで唇を噛んでいる。気持ちよくなんてない。泣きすぎて目が痛い。そこに涙の熱が染みてもっと痛い。全然気持ちよくない。胸が苦しい。どうしてだか心がキュウッと締めつけられ続けてる。
もう、どうしても泣きやめない。
心が辛い時に人に優しくされると、もっともっと泣けてきてしまう。そんなこと、初めて知る。
「……どうして、どうして私なんかに、優しくするの?」
やっとの想いで出した自分の声は震えてる。
「私なんか……。スズは、悲しいこと言うね」
「……だって、そうだから」
「私なんか、いなくなればいい? わかんないけど、そこに続く言葉ってそんな感じ?」
「……うん、そう思ってる。雨川さんにはわからないよ」
卑屈な自分が嫌になる。
「……」
せっかく優しくしてくれたのに、トゲのある言い方をしまった自分が嫌になる。嬉しいのに、本当は優しくしてもらえて嬉しいのに。
だけど人気者の雨川さんに私の気持ちがわかるわけがないし、もっと言えばそんな雨川さんと私がこれから仲良くなれることなんてまずないのだ。期待なんかしたくもない。だから、期待させるような態度をとらないでほしい。
「……ん、でもさぁ、そんなこと言ったらさぁ」
少しの沈黙の後で、雨川さんが出した声はやけにあっけらかんとしている。
「スズの気持ちが私にわからないとの同じように、私の気持ちだって誰にもわからないよ? あぁぁこの人だ、この人となら分かり合えるって思ったこと、私だってまだたったの一度もないもの」
「……雨川さんが? だって、友達いっぱいいるじゃない」
「友達はいるよ。でも、それとこれとは違う」
「それも、よくわからない……」
「友達とは、一緒にいると楽しいから一緒にいる。でも、ここは私がいる場所じゃないって気持ちがずーーーっと私につきまとう。学校の中には、まずない。だからこうして時々、保健室に避難してる。そういう意味では、スズも一緒でしょ?」
「ちょっとよく、わからない……」
「ほらね? 私、いっつも人にそう言われる。アミにも言われるよ。だけど、私なんか……とは思わない。スズも思わないでよ。だって、私たちの人生なんて本当の意味ではまだなーんにも始まっちゃいないんだから!! すべては、オトナになるまでの辛抱よ!!」
雨川さんは、私が想像していた以上に変わっている。友達が多くて人に好かれているという理由で、私とは違う星の人だと思っていた。でも彼女は、自分の世界にたった一人で住んでいるという感じがする。そう思ったら、自分のことを話しても大丈夫かもしれないという気持ちになる。
「オトナになんか、なりたくない……」
ウソでしょ、みたいな顔をして私を見ている雨川さんの方が私には、ウソみたい。
「それにこの人生、始まってもう12年も経つよ? この中がもう私には辛いよ……」
続けて言いながら泣きそうになったところで、「え!!?」と雨川さんが声をあげた。大きな目をさらに見開いて、
「ならスズ、もうキスしたことあるの? 生理は? もしかしてもうきてるの!?」
「……な、なんでそうなるの!?」
ビックリしすぎて笑っちゃった私に、「シッ」と雨川さんが人差し指を自分の唇に押し当てる。
ここは、保健室。簡易的で粗末なベッド。
パリッとしすぎた硬い質感のシーツの上。
隣のベッドを仕切るカーテンは、
30センチくらい開いている。
小学4年の冬に初潮がきたから、生理とはもう2年の付き合いになる。今も生理中でお腹の奥に時々鈍い痛みがある。
その事実を告げた途端にキラキラとした目で私を見つめはじめた雨川さんを、私はとても不思議な気持ちで眺めてる。
<つづく>


作家。1981年生まれ。ニューヨーク、フロリダでの海外生活を経て、上智大学卒。25歳でデビュー以降、赤裸々な本音が女性から圧倒的な支持を得て著作多数。作詞やドラマ脚本も手がける。最新刊は『目を隠して、オトナのはなし』(宝島社)。8歳の長男、6歳の長女のママ。
Instagram: @lilylilylilycom