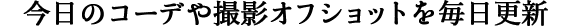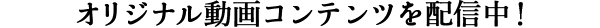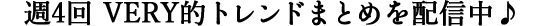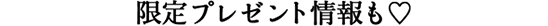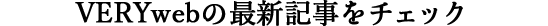お待たせしました。あのLiLyさんの連載が始まります。
LiLyさんのセックスシリーズ3部作「In Bed with LiLy」「Sex Talk with LiLy」「Ninpu Talk with LiLy」に続く、「Girl Talk with LiLy」のテーマはearly teensの性の目覚め!
母から娘への「自分の好奇心も身体も大切にする」贈り物エッセイ♡
まずは、9月号誌面に掲載したイントロダクションから、そして第一回へと続きます。

12 歳の女の子だった頃のこと、覚えていますか?
どうしてそんなに女であることを楽しめるのか、と聞かれるたびに思い出す夜がある。
あれは10歳、3つ年下の弟と一緒に入ったいつもの夜の風呂上がり。「あなたにだけヒミツの話があるの」と、母がこっそり私に言った。弟がいない時に、「渡したいものもある」と。
「なに?」。すぐに聞き返した私に、母はシッと指を口元に当ててハナシの特別さをにおわせた。
―――そして、弟が眠りについたあとで女同士の数分間が訪れた。
母の口から、生まれて初めて聞いた生理のこと。手渡されたのは、白いリボンがかかったピンク色の小さな本。
母からカラダのことを聞くのは、なんだか少し気まずくて恥ずかしかった。だから本を受けとるとすぐに、私は階段を駆け上がって自分の部屋のドアを閉めた。
―――そこからはもう、夢中で読んだ。
ここから自分のカラダがどんどん女っぽく、つまりはおっぱいが大きくなっていくこと。月に1度、生理というモノがくるようになること。
母が階段をあがってくる足音が聞こえると、パタンッと本を閉じて枕の下に隠して寝たふりをした。足音が遠ざかると、また本を開いてこっそりと浸った。
恥ずかしくて、なんだかエッチなことにも感じて、胸のドキドキが止まらなかった。
その夜以来、飽きることなくずっとずっとそんなふうにピンク色の本を、こっそりと深く読んでいた。まるで、エロ本を読む中学生の男子みたいにソワソワしながら、母にもらったその本を母に隠れてドキドキ読んだ。
―――10歳からの2年間。
恋に焦がれるようにして、初潮を待った。
そう、女になることに対して、恋に焦がれるような気持ちでいた。その日が来ること、サンタさんがくるクリスマスの不思議と同じように思っていた。ううん、違う。サンタさんを待つコドモ心よりも、ずっとずっとカラダの芯なる場所が熱くなった。
「ねぇ、お母さん、もしかしたらもうきているのかもしれない。ただ、パンツについた血を私が見逃しているのかも」
もう、待つことにしびれを切らした私は、母に真剣に小声で相談した。母は目を丸くして、優しく笑った。
「大丈夫よ、絶対に見逃すことはないから」、「ふぅん、そうなんだ」。
―――初潮がきそうで、まだこない。
その頃、父親の仕事の都合で引っ越したニューヨークにて、両親は離婚の危機を迎えていた。毎晩凄まじい喧嘩をくりかえし、まだ幼い弟は自分のベッドの中で体を丸めて泣いていた。
オトナのくせに、親のくせに、ガキみたいな怒鳴り合いを繰り返してまだ小さな弟を傷つけている両親のこと、許せなかった。
コドモにとって、両親の喧嘩というのはまるで世界の終わり。地獄、そのもの。
だけど今思えば、彼らは当時まだ30代後半。
―――父と母でありながらも男と女真っ盛り。
「男女の喧嘩は犬食わないって昔から言うのよ。あなたが入って来ると余計にこじれるから割り込んでこないでよ!」
「は? 人に迷惑かけておいてバカなんじゃないの? 早く大人になってこんな家出て行ってやるッ!!」
―――初潮がきそうで、まだこない。
子どもでいることに心底うんざりした。いつもは優しいお母さんが、女の顔に豹変する瞬間がダイキライだった。家の中で男女の喧嘩に巻き込まれて傷ついて一人で泣くのは、あまりにも寂しかった。
だけど母が、女の顔で父に怒鳴り散らしているのを見れば見るほど、ドラマの主役は女である母だと感じた。私がオトナになったら、あんな風には絶対にならないと心に誓いつつ、やっぱり早くオトナになりたいと心底思った。
だって、コドモの私は傍観者。コドモである限り、私の人生は幕すら開けない。
早く私にも生理こないかな。
早くおっぱい大きくならないかな。
色っぽい女のカラダになって、素敵なヒトと恋がしたい。
もちろん赤ちゃんはできないように、キスだけをして結婚する。
自分の未来に夢をみることに夢中になると、両親の喧嘩で泣いていることなんてアホらしくなってきた。だって、私がしている喧嘩ですらないんだから。他人のドラマで傷つくなんてバカみたい。
私の貴重なナミダは、自分のドラマで流すのよ。
―――12歳。
初潮はきそうでこなくて、ブラジャーはつけてもいいけどまだそんなにはいらなくて。精神的にはもうコドモとは呼べないくらいオトナだけれど、ティーネイジャーの仲間にすらまだいれてもらえない。
小6、女子。
恋愛対象に是非いれたい存在であるクラスの男子との精神年齢は、あいにく日を追うごとに離れてく。同じ目線で会話ができる女友達は好きだけど、互いになんともいえないライバル心もあったりして疲労する。
―――あの頃、ほんとうに独特のアンバランスを抱えていた。
誰かに思いっきりホンネを話して、「大丈夫だよ」って強い力で抱きしめてもらいたかった。だけどそれをして欲しい相手は、両親ではもうなくて。だけどまだ恋人がいるわけでもないから、ひとりぼっち。時々どうしようもなく、途方にくれるくらい心細かった。
ガールトーク。
あの頃、誰かに言いたくても言えずにいた本当の気持ちと、あの頃を生きる女の子たちに伝えたいこと。
女を楽しんで生きていると人から言われることが多い私は実際のところ、すごく楽しいと思うのと同じくらい、苦しさも感じながら生きている。
だけど、一つだけハッキリわかること。
それは、「女」という生き物に「恋」していた少女時代の気持ちが、その後の人生に最高の影響を与えてくれた事実。
だって、そうでしょう? ずっと夢みていたスターに遂になれたなら、自分をとても誇りに思う。それと同じように、ずっと恋い焦がれていた女に遂になれたなら、自分をとても大切にする。
―――ピンク色の一冊の本。
探してみたけどみつからない。今となってはタイトルも思い出せない……。
あれは、娘に贈った母の気持ちとセットで、私の人生のギフトだった。
もらったのは、胸がドキドキする種類の「憧れ」。
その感情そのものが、そのあとの人生にたくさんの幸福を運び込む魔法。
8歳の息子と6歳の娘、ふたりの母になった36歳の私は今、母からもらった愛のバトンを受けわたす気持ちでペンをとる。
誰かにとっての、そんな本になることを夢にみて。


「ねぇ、次の授業サボって、保健室いかない?」 by キキ
キスは甘い、というウワサは本当なのかな。ツバって甘くはないから、相手のことを好きな気持ちが味覚を錯覚させるのかな。みかく、さっかく。ゴロがよくって、響きもオトナで、なんだか素敵。
そんなことを考えているわたしの目の前の黒板には、白いチョークでサラサラと歴史の年号が書かれていく。テストに出るから覚えたほうがいいのはわかっているけど、頭の中では昨日みた恋愛ドラマのキスシーンが繰り返し再生されている。
外は、雨。傘なんて、ささない。濡れる、二人。
男の人が女の人の首筋に手をやって、そっと優しく彼女の顔を自分の顔へと近づけた。そして————ッ!
あぁ、ヤバイ。もうダメ、溶けそう。
わたしもあんなにもロマンティックでエッチなことをする日が、くるのかな。ううん、くるわけないって思っちゃう。だけどいつか、くるんだよね? あぁ、だけどそんなのはスマホ画面か頭の中の妄想、つまりは夢のまた夢の世界の話だから、現実に起きるわけがないってどうしても思っちゃう。
「雨川さん」
担任の南野に名前を呼ばれてハッと我にかえる。
「……ノートをとってくださいね」
静かな声で注意するところは、南野の良いところ。前の担任の島田は怒鳴りグセがあるから大嫌いだった。
「あ、はい!」と慌てて答えたら声が大きくなってしまって、後ろの席のアミがクスクス笑う声が聞こえてきた。わたしはアミにサインを送るように、わざと大きく肩をすくませる。そして、目の前でわたしを見ている南野の手前、鉛筆を手に黒板を見ているポーズをとる。
『1931年 満州事変』
これは先生の余談だからノートに書かなくていいぞ、というところを南野はピンク色のチョークで書く。わたしはとりあえず、大事な白チョークの部分よりも目立っているそこをノートに書く。
南野は40代の男性教師で歴史マニア。「知識が多すぎてついつい小学生の授業の枠から脱線してしまうオレ」を自身が気に入っているタイプ。つまりは自己満。授業がすこぶるつまらない。
あーぁ、恋の授業があればいいのに。
そしたら手をあげて質問したいことがたくさんあるし、たとえノートを取らなくたってすべてその場で覚えちゃうのに。
あ、でも南野の恋バナなんか聞きたくないかも!! オエ〜。
そう思ったら吹き出してしまいそうになったので、下唇をキュッと噛んで笑いをこらえて前を向く。
黒板に向き合って白いチョークを持つ南野の手には、結婚指輪。ということは、南野もキスをしたことがあるってことだ。南野にもできるなら、きっとわたしにだってキスをする未来くらい用意されているはずだ……ッ!
未来がなんだか希望に満ちてきて胸がドキドキしはじめた。
「雨川さん、なにがおかしいんですか?」
ヤバイ。気づいたら小さく笑っていたらしい。
南野が振り返ってわたしを見ている。二度目の注意を受けたことで、今度は後ろの席のアミが吹き出した。アミが笑った、と思ったらわたしは爆笑しそうになってしまって、慌てて口を手で覆ったが遅かった。
「雨川さん!?」
南野の静かな声が怒りを含む。マズイ。
「あの、えっと、満州事変、って書いてあるのを見て、母が東京事変を好きなことを思い出したら笑ってしまいました」
苦しい言い訳。でも、あなたでもキスを経験できたならわたしだっていつか、とあなたのその冴えなさがわたしの希望になりました、とは口が裂けても言えない。
やれやれ、とでもいうように首を横に大きく振ってから、南野は授業に戻った。席替えで教卓の真ん前の席にされたことが物語るように、わたしと真後ろにいるアミはセットでクラスの問題児扱いされている。
マセていて生意気、というのが理由だろうとわたしのママは分析した。そしてママは、そんなわたしとアミに「胸キュン」するという。そう、ちょっと変わった親なのだ。が、わたしが南野をバカにした発言をすると、「人をナメるな!」と突然キレられる。
南野に限らない。テレビに出てくる芸能人を見て「ダサい」とか「キモい」とか言うのも禁止されている。「パッと見で他人を下に見てバカにできるほどお前はエラいのか? そういうところがまだクソガキ」だと怒られる。
ママが言っている意味はわかるけど、だから気をつけてはいるけれど、でも「キモい」とか「オエ〜」とか「ダサ〜」とか、心では思ってしまうことはあるよ、うん。
そういえば、南野はママと同じ40代。でも、さっきわたしが言った「東京事変」に無反応だった。知らなそうな雰囲気だった。
やはり、とわたしは心の中で思う。カルチャーにうとい大人は、イマイチ信用ができない。
あ、でも南野は歴史には詳しいのだ。南野からしたら、“歴史にうとい事変ファン”のママのほうに不信感を持つのかも。
こういうのを相性と呼ぶのかもしれない。どちらが良い悪いではなく、どちらがダサいイケてるでもなく、ただ単に「合う・合わない」。そういうのってある。それもママがよく言っている。
ちなみに「東京事変」は最高のバンド。ママが大ファンで、わたしもつられるようにして大好きになった「椎名林檎」率いるバンド。林檎は美しき天才。
あ、林檎! 恋を教わるなら、林檎みたいな先生がいい! 林檎の恋の授業、すっごく受けたい! 誰よりも積極的に授業を受けるし、林檎の言葉はその場で暗記できる自信があるから、テストでの満点も必至。東大にだって行けちゃうな。
わたし、今、恋とかキスとかに興味があるんだもん。興味がないことばかりを暗記しろって大人に言われることが、とっても苦痛。
早く好きな人とキスとかできちゃう大人になりたい。未来がたのしみで泣けてくる。小学校の教室の中に座っている今の小学生の自分なんか、パパッと早送りしちゃいたい!!
一人で勝手に興奮したところで教室の時計を見たら、三限終了まであとまだ30分もある。
わたしが知りたいのは自分の未来なのに、南野が日本の歴史について延々と話している。うんざりした気分で教室を見わたすと、通路を挟んで隣の席にいる鈴木さんがジッとうつむいていることに気がついた。
よく見たら、広げた教科書の上にポタポタと涙が落ちている。上手に隠しているので、鈴木さんの異変にはまだ誰も気づいていない。
大人しくて、クラスの中で目立つタイプでもなくて、ちゃんと話したことはない鈴木さん。どうしたんだろう。なにがあったんだろう。もしかして誰かにイジメられている?
「ねぇ、次の授業サボって、
一緒に保健室いかない?」
わたしはノートのはじを小さく破ってそう書くと、南野にバレないようにそーっと腕を伸ばして鈴木さんにメモを差し出した。
優しさ、というのもあるかもしれないけれど、次の授業はこれまたわたしの興味から遠い「理科」なのだ。ちょうど保健室に逃げ込もうと思っていた。
アミとわたしが親友同士なのは誰もが知っていることなので、ここでアミとクラスを抜ければサボリとバレる。鈴木さんの涙の理由も知りたいし、わたしに力になれることもあるかもしれないし、我ながら良いアイデア!
メモを読んでビックリした顔をして、私のほうを見た鈴木さんの目はやっぱり真っ赤。ひとりで泣いていたのだ。かわいそうに。たすけになりたい!
鈴木さんがわたしのことをどう思っているかはわからなかったけど、「キキは聞き上手ね」ってママにいつも褒められるからそこには自信を持っている。
「カラダがつらい時だけじゃないんだよ、
ココロが悲しい時も行っていいんだよ、保健室! 一緒いこ♡ 」
またノートを破ってそう書き込んで、まっすぐ腕を伸ばしてこっそり渡す。
お節介だと思われるかもしれない、と手渡した後で一瞬不安に思ったから、メモを読んだ鈴木さんが静かに頷いてくれたのを見て、わたしはとっても嬉しかった。
<つづく>


作家。1981年生まれ。ニューヨーク、フロリダでの海外生活を経て、上智大学卒。25歳でデビュー以降、赤裸々な本音が女性から圧倒的な支持を得て著作多数。作詞やドラマ脚本も手がける。最新刊は『目を隠して、オトナのはなし』(宝島社)。8歳の長男、6歳の長女のママ。
Instagram: @lilylilylilycom