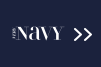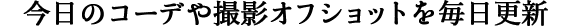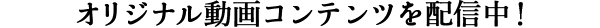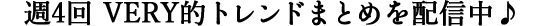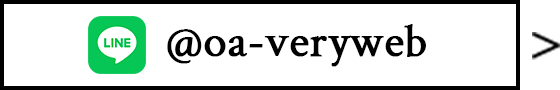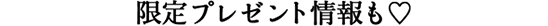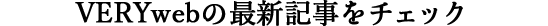「やりたい」と言ったから始めたのに、「今日は行きたくない」と言ったり、やめたい理由が「面倒だから」にモヤモヤしてしまったり。励ます?休ませる?やめる?習い事スランプ期のママのお悩みについて、専門家の先生たちにアドバイスをいただきました。
こちらの記事も読まれています
習い事をする意味って?
親の“心構え”を教えてください!
習い事は、親以外の大人からも成長の刺激をもらうチャンス
習い事は子どもの成長にとって重要な「共同体意識」を得られるとてもいい機会。種類は問わないので、ぜひやらせてあげてください。幼児はどんな習い事があるか知らないので入口は親が示してあげる必要がありますが、大切なのは、子どもの意思を尊重すること。親の役割は、やりすぎて疲れないスケジュール管理と、子どもが習い事を好きになるかどうかの見極めです。時として、習い事で出会う大人にもらった核心的な一言が、子どもの一生を支える言葉になることもあります。そんなチャンスを増やせたらいいな、という気持ちでママたちも向き合えたらいいですね。

小児科医/お茶の水女子大学名誉教授
榊原洋一先生
医学博士。発達障害研究の第一人者であり、現在でも、子どもの発達に関する診察、診断、診療を行っている。
親が一緒に向き合った経験や思い出が子どもの総合的な成長につながります
習い事は特定の分野に効率よく触れられるものではありますが、むしろ習い事での嬉しい・悔しい思いを親子の共同体験として楽しむことが、子どもの全体的な成長に繋がります。やりたくないことをやらせて伸びる子はいません。「それはやってみたい」と思える小さな目標を一緒に立て、少しずつクリアしていくことで自信がつき、「やれた気」=やる気が育まれます。いい先生は親とは違う目線で子どもを見守ってくれる子育てパートナーです。ママたちも、ハウツーや言語コミュニケーションに頼りすぎず、我が子をよく観察して、その言葉の背景を探ってみてください。

教育家/見守る子育て研究所®所長
小川大介先生
教育家。子ども本来の力を見つけ出す「見守る子育て」を提唱し、講演、人材育成、文筆業と多方面で活動。
取材・文/八重沢友香子 編集/清水 環 画像/AC
*VERY2025年4月号「習い事スランプ期の向き合い方」より。
*掲載中の情報は誌面掲載時のものです。